仕事にはストレスや悩みはつきものです。
といっても、適度な休息も気分転換もなく頑張り過ぎると、心身の疲れはピークに達してしまいます。こんなときは「休職」も選択肢のひとつです。が、「休職したら終わり」なのでは?と不安で、踏み切れないこともありますよね。この記事では、休職制度について、期間や手続き方法、気になる給与の取扱い、休職中にもらえる手当についても、できるだけくわしく解説します。
Contents
休職とは
会社を休む言葉には、「休職」以外に「欠勤」や「休業」という言い方もあります。では、どのような状態を「休職」というのでしょうか。
休職とは、雇用契約が維持されたうえで、会社から労働の義務を免除され、仕事を休むことをいいます。休む理由は、プライベートの傷病や留学などの個人的な事情です。法律上の義務はないため、休職制度を設ける、設けないは会社の自由です。社員の福利厚生のために設けるケースもあります。
ちなみに「独立行政法人 労働政策研究・研修機構」の2022 年の調査によると、従業員規模 10人以上の企業 20,000 社のうち、病気休職制度のある会社は、全体の69.5%となっています。また、正社員規模が大きい会社のほうが、病気休職制度がある割合は高くなっています。
比較的多くの会社で導入が進んでいる休職制度ですが、必ずしもすべての従業員が対象になっているとは限りません。前述したように、休職制度は、会社が自由に制度設計ができるため、たとえば、対象者を期間の定めのない契約である正社員に限るとすることも可能なのです。雇用形態によって休職制度を利用できないケースもあるので、就業規則などの確認は必要です。
休職と欠勤の違い
では、休職と「欠勤」はどこが違うのでしょうか。
欠勤も、従業員の個人的な事情による休みですが、休職の場合と違って、会社に労働の義務を免除されているわけではありません。つまり、会社に正式に許可された休みかどうかが、休職との違いです。
また、休職は、会社によっては、独自の手当が出るケースもありますが、欠勤は基本的に無給です。さらに欠勤が長期に渡ると、雇用契約に影響することもあります。
休職と休業の違い
一方、休職と「休業」の主な違いは、休む理由です。
休職は、プライベートの病気やケガ、留学など、個人的な都合が理由なのに対し、業績不振による自宅待機などの会社都合、または出産や育児、介護など、法的な制度に基づいて休む場合が休業になります。また手当についても、休業の場合は、法律の定める条件を満たせば手当や給付金が支給されます。対して、休職では無給であることが多いです。
法令で定められている主な休業
- 会社都合による休業(労働基準法第26条)
- 産前産後休業(労働基準法第65条)
- 育児休業(育児・介護休業法第5条)
- 介護休業(育児・介護休業法第11条)
休職=クビではない
ところで、休職するとクビになる、つまり解雇になるのでしょうか。
結論からいうと、休職=クビではありません。会社が傷病休職制度を設ける主な目的は、一定期間、解雇を猶予して、従業員の回復を待ち職場復帰させるためです。このため、休職したからといって、即クビになるわけではありません。
ただ、多くの会社では、就業規則に、休職期間が満了しても復帰できない場合は、「退職」または「解雇」とすると規定しています。このため、休職期間が満了した段階で、身体の調子が戻らず、職場復帰できない場合、就業規則に「解雇」と規定されていれば、解雇となります。
出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「治療と仕事の両立に関する実態調査 (企業調査)」
休職のメリット・デメリット
ここからは休職のメリットとデメリットを解説します。
休職のメリット
休職のメリットは、次のとおりです。
- 仕事から離れ、落ち着いて療養できる
仕事をしていると、業務成績やノルマ、職場の人間関係など、悩みはつきません。また、通院も二の次になってしまう恐れもあります。いったん仕事から離れ、療養に専念することで、早期回復も見込めるでしょう。
- 心身ともにリセットできる
一定期間休むことで、ストレスや悩みから開放され、心身ともにリセットできることもあります。また、自分や仕事について、思いがけない気づきがあるかもしれません。
- 自分の将来や今後の仕事人生について、じっくり考えることができる
家と職場の往復だけの日々では、目の前のことにとらわれ、本当はどうしたいのか、自分の気持ちがわからなくなることもあります。休職して自分に向き合うことで、再び仕事や人生にチャレンジする力となることもあります。
休職のデメリット
休職には、次のようなデメリットもあります。
- 収入が大幅に減少する
休職中の給与については法律上、会社に支払い義務はないため、休職期間中は無給の場合も多いです。要件を満たせば、労災給付(業務上または通勤が原因の傷病)や傷病手当金(プライベートの傷病)などの対象になりますが、給与の全額を保障する金額ではありません。
さらに、詳しくは後ほど述べますが、休職期間中も社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)や住民税は免除されないため、払い続ける必要があります。そのため、手取りは大幅に減る可能性が高いです。
- 人事評価に影響することがある
実績や実務の経験年数を評価基準にあげている場合、休職期間は実績を積むことができず、経験年数にもカウントされないので、昇進や昇格に影響を及ぼす可能性があります。
ただ、会社によっては、休職期間を評価算定期間から除くなど、休職が評価に不利に働かないように規定している場合もあります。また、休職を理由とした低評価は、労働契約法第34条の公正評価義務に抵触する可能性もあることから、必ず影響するとは言い切れません。
- 復職が難しく感じ、結果的に退職することもある
一定期間療養に集中し、復職を目指すための休職制度ですが、復職せずに退職に至るケースもあります。病気休職制度利用者の2人に1人が退職に至っているという調査結果もあり、復職せずに退職する可能性は低くないといえます(2012年 独立行政法人労働政策研究・研修機構「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査」)。
だからといって無理して休まないのは、あまりおすすめできません。周りから取り残されそうに感じて不安なときも、自分の心と体の声に耳を傾け、自分自身を守る選択をするようにしましょう。
出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査」
休職期間は
休職の定義やほかの休みとの違い、メリット・デメリットがわかったところで、ここからは具体的に、休職の期間について確認していきます。
休職期間は会社ごとに異なる
休職制度は会社の独自規定になるため、休職期間も会社ごとに違います。
ちなみに、「独立行政法人労働政策研究・研修機構」の2022年の調査では、休職期間の上限は「6か月超えから1年まで」が17.2%で最も多く、ついで「1年超えから1年6か月まで」が16.2%となっています。
延長はできる?
休職期間は、就業規則などに規定されている上限までは延長が可能です。たとえば就業規則に、休職期間の上限が6か月と規定されている会社で、3か月間休職していた場合は、最大プラス3か月間、期間の延長ができます。
ただし、延長が認められるためには、延長期間が具体的に記載された医師の診断書や、近いうちに復職できる目処が立っていることが条件であることも多く、無条件で延長できるのではないことに注意しましょう。
出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「治療と仕事の両立に関する実態調査 (企業調査)」
主な休職理由
次に休職の理由として主なものを紹介します。
私傷病休職
「私傷病休職」とは、業務中や通勤以外が原因の病気やケガで休職する場合をいいます。
【例】
- 休日に友人とスキー旅行に行ったところ、雪山で転倒し足を骨折。一定期間、入院が必要となったため
- プライベートの事情が原因でうつ病となり、療養のため休職が必要となったため
私傷病休職は、労災給付の対象外となるため、病院の診察料・薬代は無料にならず、休職期間中の給付金も労災からは出ません。ただし、一定の要件を満たすと、健康保険から「傷病手当金」という給付金が受給できます。傷病手当金については、後ほどくわしく述べます。
自己都合休職
「自己都合休職」とは、プライベートでの希望や事情が理由による休職のことです。
【例】
- 災害復興支援のボランティア活動に参加するため
- 青年海外協力隊に参加するため
- 資格取得のため専門学校に通うため
こちらも無給の場合が多いですが、ボランティア活動など社会貢献的な意味合いのある理由の場合、「ボランティア休暇」など、給与の一部支給のある休暇制度を設けている会社もあります。
留学休職
キャリアアップや自己啓発のための海外留学を会社に認められた場合は、「留学休職」となります。基本的に休職期間中の給与は支給されませんが、福利厚生の一環として会社に海外留学制度がある場合などは、一定の給与や学費などが支給されることもあります。
事故欠勤休職
「事故」という言葉から、交通事故による傷病が理由の休職のように思われますが、そうではありません。
「事故欠勤休職」とは、傷病以外の自己都合による欠勤が、一定期間に及んだため、休職措置が取られる場合をいいます。代表的な例は、刑事事件を起こし、逮捕・勾留された場合です。
起訴休職
「起訴休職」は、刑事事件の被告として起訴された際、一定期間、もしくは判決確定まで休職扱いとする制度です。休職期間中に会社と協議のうえで退職となったり、刑事処分の確定後、懲戒処分が科されることもあります。
出向休職
「出向」は、従業員が元の会社と何らかの関係を保ちながら、別の会社で勤務することです。人事交流やキャリアアップなどのために行われることもあります。元の会社に籍を残したまま、出向先の会社で働く「在籍型出向」と、出向元を退職し出向先に完全移籍する「移籍型出向」の2種類があります。
「出向休職」は、在籍型出向の場合の制度で、出向先の会社で勤務している間、出向元の会社では休職扱いとなります。
組合専従休職
「組合専従休職」とは、労働組合の業務に専念する(組合専従)ときに適用される休職制度です。専従期間中の給与は、会社ではなく労働組合の組合費から支給されます。
公職就任休職
「公職就任休職」とは、従業員が市町村長や議員などの公職に就くため一定期間、仕事から離れることを休職として認める制度で、会社から一定の給与が支給される場合もあります。会社としては、授業員が公職を経験することによって、地方公共団体や国との関係を築けるため、制度があれば、比較的認められやすい面もあるようです。
休職中の給与・賞与はどうなる?
会社には様々な休職制度があることがわかりました。ここで気になるのが、休職した場合の給与や賞与の取扱いです。この章では、休職期間中の給与・賞与の一般的な取扱いを解説します。
給与は基本的に無給
民法第624条を根拠とする「ノーワーク・ノーペイの原則」(「働かなかったら支払わない」)により、原則として、会社には、休職中の給与支払い義務はありません。そのため、基本的に休職期間中は無給であることが多いです。
ただし、給与を支払ったとしても問題はないので、「ボランティア休暇」や「留学休職」など、特別に給与や手当が支給されるケースもあります。
また、傷病による休職の場合、支給要件を満たせば、業務中や通勤が原因の場合は労災保険から、プライベートの病気・ケガの場合は健康保険から、それぞれ給付金がもらえます。
賞与は評価期間に注意
賞与についても、休職期間中はあまり期待できません。ただし、就業規則などで賞与の評価の対象となる期間や支給の基準が規定されている場合は、休職前の勤務期間を対象に評価され、賞与が支払われるケースもあります。
休職中の社会保険料・税金の取扱い
給与が無給だった場合、とくに気になるのが、毎月控除されている社会保険料や税金です。ここからは、休職中の社会保険料と所得税・住民税の取扱いを見ていきます。
社会保険料
休職期間中も社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は原則、免除されません。そのため、給与天引きのできない無給の場合、たとえば次のような方法で会社に支払う必要があります。
- 毎月一定期日までに会社指定の銀行口座に振り込む
- 復職後に月給や賞与から控除する
支払い方法は、あらかじめ就業規則などで確認しておくと安心です。
ちなみに3歳までの子の育児休業を取得した場合は、一定の要件を満たし、会社が届け出をした場合は、社会保険料は免除されます。
雇用保険料は給与額に雇用保険料率をかけて算出するので、無給の場合は発生しません。
所得税・住民税
所得税も給与からの源泉徴収のため、無給の場合は発生しません。ただし、住民税については、前年の所得金額から算出しているため、無給でも支払い義務があります。住民税を給与天引で支払っている場合(特別徴収)は、支払い方法を確認しておきましょう。
休職中にもらえる手当
多くの場合無給となる休職中は、生活費も心配なところです。が、休職の理由によっては、国から給付金がもらえるケースもあります。以下、休職中にもらえる手当金・給付金について、できるだけくわしく解説します。
傷病手当金
「傷病手当金」は、健康保険の被保険者が、プライベートの病気・ケガの療養のため、会社を連続して3日間休んだ場合、会社を休んだ日に対して支給される給付金です。
同じ病気やケガにつき、支給開始日(休業4日目)から通算1年6か月の間もらえます。
1日あたりの支給額は、休業前給与の3分の2に相当する額となります。
なお、くわしい計算式は次の通りです。
1日あたりの支給額=休業開始前12か月の「標準報酬月額」の平均額÷30日×2/3
※標準報酬月額
社会保険料算定の基礎となる「保険料額表」の等級の金額。給与の平均額等をこの表に当 てはめることで等級(標準報酬月額)が決まります。被保険者期間が1年に満たない場合 の計算方法など例外もあるので、正確な額は健康保険組合等に確認してください。
【例】
月額平均給与:25万円
標準報酬月額:26万円
一日あたりの傷病手当金:26万円÷30日×2/3≒5,778円
なお、有休処理した場合など、休んだ日に給与が全額支給されていた場合は、傷病手当金は支給されません。また、給与の一部支給の場合は、その額が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。
傷病手当金をもらうには、健康保険組合等に「支給申請書」を提出する必要がありますが、申請書には医師の記入欄があり、会社の証明も必要です。さらに手続きには約2週間、書類に不備などがあればそれ以上かかる可能性もあるので、注意しましょう。
その他、休業理由によってもらえる手当
その他、被保険者要件など一定の要件を満たせば、各種保険から、手当金・給付金が受給できます。次の表をご参照ください。
| 保険 | 手当 | 条件 | 支給額※ |
| 労災保険 | 休業補償給付+休業特別支給金 | 業務上または通勤が原因の病気やケガによる休業4日目以降 | 給与の60%+20%=80%相当額 |
| 健康保険 | 出産手当金 | 女性の被保険者が、出産のため会社を休んだ場合、産前42日・産後56日間に対して | 給与の3分の2相当額 |
| 雇用保険 | 育児休業給付金 | 原則1歳未満の子を養育するために休業した場合 | 給与の67%(半年後からは50%)相当額 |
| 雇用保険 | 介護休業給付金 | 要介護状態(2週間以上にわたり常時介護を必要とする)にある家族を介護した場合、同じ家族につき3回・93日を限度 | 原則として給与の67%相当額 |
※給与が支給された場合は支給額が調整される。給与全額支給なら支給なし、一部支給の場合は差額支給。
出典:全国健康保険協会 岩手支部「傷病手当金について(制度説明)」
出典:厚生労働省「労災保険 休業(補償)等給付傷病(補償)等年金の請求手続」
出典:厚生労働省「産前・産後休業中、育児休業中の経済的支援」
出典:厚生労働省「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」
休職までの流れと手続き
休職するには、事前準備も必要です。ここからは、スムーズに休職に入っていけるよう、休職までの流れと具体的な手続き方法を解説します。
休職までの4つのStep
休職の手続きには、主に次の4つのステップがあります。
Step1就業規則を確認する
まずは、自分の会社に休職制度があるかを就業規則で確認しましょう。
ある場合は、自分の状況が制度の定める条件に該当するかも、チェックする必要があります。
たとえば、「欠勤が暦日で30日以上に及ぶ」といった日数条件があったり、勤続年数によって休職期間の上限が違う場合もあります。十分注意しましょう。
また、就業規則に、休職中の社会保険料の支払い方や休職中の連絡先、復職の流れなどが記載されている場合は、忘れずに確認しましょう。
Step2病院を受診し医師の診断書をもらう
病気やケガが理由の場合は、病院で医師の診断書をもらいます。診断書の費用は、健康保険の適用外で全額自己負担です。病院ごとに費用は異なり、数千円から1万円を超えることもあります。また、発行までに数日から1週間以上かかる場合もあるため、可能であれば病院に事前に確認しておくと安心です。
Step3上司に休職の意思を伝える
一般的には直属の上司に伝えます。ただし、直属の上司との関係悪化が理由の場合は、無理せず、人事部や総務部の担当者などに伝えるのもひとつです。
Step4必要書類を提出する
上司や人事担当者等の指示に従い、必要な書類を速やかに提出しましょう。ちなみに、病気・ケガの休職では、休職届(休職願・休職申請書)と診断書を提出するケースが比較的多いようです。
書類は直接提出が原則ですが、体調等の関係で出社できない場合は、会社に確認のうえ郵送で提出するようにしましょう。
必要書類が受理され、正式に休職が認められると休職期間に入ります。
休職に入る際は、休職中の連絡方法や連絡先を確認しておきましょう。休職中、定期的に病状などの報告を求められるケースもあります。どれくらいの頻度で誰に報告をするかなど、確認しておくと安心です。
休職中の過ごし方
休職中は、これまでの仕事中心の日々から環境が一変します。とくに休職当初は、休むことに罪悪感を感じてしまいがちです。それでも、まずはゆっくり休むことが大切です。
また、「何かしなければ」と焦ってしまうこともあるかもしれません。不安や焦りを感じたときは、主治医や家族、友人など信頼できる人に話を聞いてもらうのもひとつです。
休職は自分らしく生きるための準備期間
休職期間は、今後の人生について、じっくり考えることができる期間でもあります。
十分リフレッシュし、落ち着いて考えることができるようになったら、無理せず自分らしく生きていくためのプランを練るのも悪くないと思います。
実際、「一般社団法人キャリアブレイク研究所」の2024年の調査では、離職・休職(キャリアブレイク)の経験者の約60%が、キャリアブレイクが「よい転機になった」と答えています。
また、同調査の「キャリアブレイク中にやってよかったこと」のアンケート結果を見ると、「寝る」「家族と過ごす」「旅行する」「資格を取得する」など、キャリアブレイク中の過ごし方は、本当に人それぞれであることがわかります。
復職するにしても転職するにしても、休職という経験は自分の糧となり、人生に深みと彩りを与えるものだと思います。
自分らしく生きるための準備期間として、休職期間を心のとおりに過ごすために、この記事が参考になれば幸いです。
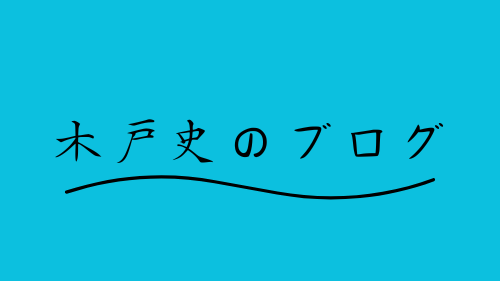
コメントを残す